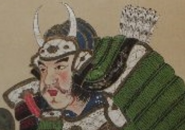実は天下も狙っていた?

画像:蒲生氏郷の肖像(上野尻酉光寺)
秀吉が領土の配分を決めるにあたり、氏郷は会津42万石を与えられ福島県に移封(移動)となった際、しばらく屋敷の部屋に閉じこもって涙を流したそうです。
家臣は「さぞ嬉しいのだろう。大出世だからな!」と感動し、部屋から出てきた氏郷に「おめでとうございます!私も自分のことのように殿の出世が嬉しいです」と言いました。
ところが氏郷は家臣に対し、「悲しくて泣いていたのさ。京都の近くにいれば天下取りのチャンスも巡ってきたかもしれないけど、遠く離れた北陸に移動するんだから二度とチャンスはない」そう答えたといいます。
つまり、嬉し涙ではなく悲観して嘆いていたのです。それから数年が経ち、秀吉が息子の秀次に関白の地位を譲って隠居したとき、家臣が氏郷に「やはり秀次殿が天下人になられましたな」と尋ねました。
氏郷は「あれは天下の器じゃない」そう言い、「天下人の器量を持ち合わせているのは前田利家さんだ。そして私にも少しはチャンスがある」そう答えたそうです。
軍記の一コマなので本当に語ったか真実は定かではありませんが、氏郷の野心が垣間見える逸話ですね。
そもそも、なぜ氏郷が会津に移封になったかといえば、伊達政宗の監視役と関東領の徳川家康の抑えとしての役割が強かったと言えます。しかし、一説によると、実力のある氏郷を京都から離したという見方もあるようです。
事実、政宗は会津を奪われた悔しさから氏郷の暗殺を企んだり葛西大崎一揆を誘発したり何かと嫌がらせしましたが、悪事が露呈され政宗は処分を受けています。
ちなみに、会津の「若松」は氏郷が名付けた地名なんですよ(旧名は黒川)。
千利休が認めた氏郷の茶道

画像:千利休の肖像(堺市博物館)
戦場で大活躍し、密かに野心家な一面もあった氏郷ですが、武芸のみならず茶道や俳句、書や絵画にも通じていた文化人でもあり、人柄の良さや人間性においても周囲から高い評価を受けていました。
たとえば、茶道の歴史書「茶道四祖伝書」には氏郷について「日本で最も気が長い男である」と記されており、また、宣教師の記録には「国家の定めや掟を熟知し、聡明で謙虚であり、誰に対しても寛容である」と書かれています。
氏郷は早くから信長に茶道を許されており、織田家では特定の家臣しか茶の湯を認められていませんでした。
やがて氏郷は千利休から茶の手ほどきを受けるようになり、その結果、利休の高弟(弟子の中で特に優れた者)7人のうちの一人に選ばれています(氏郷は利休七哲の筆頭だった)。
数年後、利休が秀吉から切腹を言い渡されて他界したとき、利休の養子である小庵を会津で保護しています。小庵がいなければ、現在の表千家・裏千家は存在していなかったと言われるほど重要な人物。
利休の死で一度は途絶えた千家でしたが、小庵が再興したことによって現在に至るまで茶道が受け継がれているのです。
さて、40歳という若さで死去した蒲生氏郷。死因については様々な説があり、はっきりと分かっていません。もし氏郷が長生きしていれば・・・、関ヶ原の戦いや大阪の陣の結果に大きな影響を与えていかもしれませんね。












































-190x190.jpg)













」-190x190.jpg)
」-190x190.jpg)





























































の消滅」-190x190.jpg)





」-190x190.jpg)



















-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)








-190x190.jpg)
-190x190.jpg)




」-190x190.jpg)





-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)
















-190x190.png)
-190x190.png)


-190x190.jpg)
-190x190.jpg)









-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)


jpg-190x190.jpg)
-190x190.jpg)



-190x190.png)
-190x190.png)






-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)
」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)







-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)











-190x190.jpg)
-190x190.jpg)



-185x130.jpg)