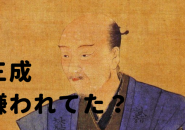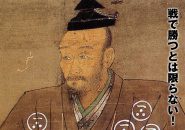戦国時代の「石高」とは?石高が多い武将は軍事力も高いのか?

加賀100万石の前田利家や会津120万石の上杉景勝など、戦国時代の大名や武将にとって「石高(こくだか)」は権威を示すステータスの一つでした。ところで、100万石って「どれぐらいの価値」があったのでしょうか。
そこで今回は、戦国時代の「石高」について復習していきたいと思います。石高を知れば当時の大名や武将の軍事力を知る参考にもなるので、覚えておくと役立つかもしれませんね。
石高とは?

「石(こく)」という単位で土地の生産高を表したものが「石高」になります。また、石高といえば米の生産量というイメージもありますが、米以外の農作物や海産物(塩も含まれる)の生産量や収穫量も石高に含まれます。
ただし、それら収穫物は米の単位で石高に換算されていたため、米の生産量というイメージが強いのかもしれません。
|
1石・・・10斗の収穫量(米に換算すると100升、または1000合。重さは150キログラム) |
そして、
|
1石の米が収穫できる土地の面積を「1反」 |
と太閤検地で定め、このときの1反は土地面積で300坪(江戸時代の1反は360坪)でした。
1石が1000合という基準になった理由は、
|
成人男性が1日に食べる米の量を3合とし、年間で約1000合 |
という計算になります。
| 1石あたり、10キログラムの米袋が15袋 |
と思えば、イメージしやすくなりますね。












































-190x190.jpg)













」-190x190.jpg)
」-190x190.jpg)





























































の消滅」-190x190.jpg)





」-190x190.jpg)



















-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)








-190x190.jpg)
-190x190.jpg)




」-190x190.jpg)





-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)
















-190x190.png)
-190x190.png)


-190x190.jpg)
-190x190.jpg)









-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)


jpg-190x190.jpg)
-190x190.jpg)



-190x190.png)
-190x190.png)






-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)
」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)







-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)











-190x190.jpg)
-190x190.jpg)