戦国最強と称される武田信玄の軍隊は本当に「負け知らず」だったのか?

画像:武田信玄の肖像(高野山持明院)
武田信玄といえば、戦後最強の騎馬隊や猛将が率いる赤備え、上杉謙信と激戦を繰り広げた川中島の戦いや信長や家康を打ち破った三方ヶ原の戦いなど、負け知らずで屈強なイメージをもつ人が多いのではないでしょうか。
WEBや書籍などでも信玄の戦歴について「生涯で負けたのは一度だけ、あとは少しの引き分けで残りの合戦は連戦連勝」といった具合にイメージ通りの評価を下している場合が多いようです。
しかし、実際のところ、信玄の戦歴は「3割が引き分け」だったことが史料や文献をたどっていくと分かります。ここで誤解しないでほしいのは、だからといって「弱かった」というわけではありません。
川中島の戦い

画像:川中島合戦図屏風「第四次川中島の戦い」(岩国美術館)
武田信玄の戦歴で、まず代表的な合戦は上杉謙信と5度にわたり(1553年~1564年の11年間)行われた川中島の戦いですが、いずれも確かな勝敗はつかずに引き分けで幕を閉じました。
そもそも川中島の戦いが勃発した原因は、信玄が北信濃(長野県北部)へ侵攻するにあたり葛尾城(長野県埴科郡坂城町)の村上義清に攻撃を仕掛けたことが始まり。
葛尾城を追放された義清は本拠地を奪還するために越後の上杉謙信に救援を求め、助けを求められた謙信が信濃に進軍して信玄と対峙することになったのです。
川中島の戦いは、ただ単に勝者と敗者という解釈ではなく、総合的に考えて引き分けと結論付けるのが妥当です。
第一次・・・1553年9月(天文22年4月)「布施の戦い」
第二次・・・1555年8月(弘治元年7月)「犀川の戦い」
第三次・・・1557年4月(弘治3年8月)「上野原の戦い」
第四次・・・1561年10月(永禄4年9月)「八幡原の戦い」
第五次・・・1564年9月(永禄7年8月)「塩崎の対陣」
もっとも激戦となったのは第四次の「八幡原の戦い」でしたが、信玄は弟の信繫や山本勘助、諸角虎定や初鹿野源五郎など有能な家臣を多く討ち取られています。
しかし、兵力で上回る武田軍※が交戦し、上杉軍は信濃から本拠地である越後(新潟県)に引き揚げ、信玄は葛尾城の奪還を阻止しました。※(一説によると武田の兵は2万で上杉は13000)
所領の獲得という点では信玄が本来の目的を果たしているので勝ちと言えますが、兵力差があるにも関わらず武田の屈強な武将らを多く討ち取ったという点では謙信に軍配が上がるでしょう。
とくに、武田家のナンバー2である信繫の死は信玄にとって大きな屈辱だったに違いありません。
武田信玄の戦歴は3割が「引き分け」

画像:歌川国芳・画「川中島百勇将戦之内」名将・武田信玄(東京都立図書館)
甲斐の虎として戦国に君臨し、足利義昭が信長包囲網を発令した際には、信長と家康は信玄によって窮地に追い込まれる(三方ヶ原の戦い)など、のちの天下取りたちを脅かす存在であったことは確かです。
とはいえ、生涯の戦歴を確認すると、ほとんどが「引き分け」で終戦していることがわかります。なぜ、引き分けが多かったのか、それには「信玄にとって人生で唯一の負け」と言われる村上義清との戦いについて知っておかなければなりません。
義清は信玄に負けて北信濃を追放されましたが、実は過去に、2度も義清に大負けしています。
1度目の「上田原の戦い」では敵地の把握をしておらず豪雪に手こずって多くの兵を失って退散。2度目「砥石城の戦い」では義清が高梨政頼と手を組んでいたことに気づかず大敗(砥石崩れとして有名)。
この教訓を生かして信玄が"戦上手”になったかといえば、そうではありません。敵と対立しても深追いせずに、ほどほどの合戦を行って「引き分け」で終わることが多くなっていくのです。
生涯に行った合戦は72回(諸説あり)ですが、上田原の戦いや砥石城の戦いを含めて3回の敗北、49回の合戦で勝利、残り20回は引き分け。およそ3割は引き分けの合戦ということになります。
向かうところ敵なしで連戦連勝というイメージが強い信玄ですが、実際には余計な深追いはせずに"負け戦"を避けるようになります。とくに人生の後半になると武力による戦いではなく、調略によって敵を負かすという頭脳戦が目立ちます。
ちなみに、3度目の戦いで村上義清を北信濃から追放したのは、武田の家臣であった真田幸隆(真田幸村の祖父)の調略によって村上氏の家臣らを寝返らせることに成功したからです。
また、信玄は古来中国の兵法「孫子」に影響を受けていたことが分かっていますが、孫子には「戦わずして勝つことが最も良い勝ち方である」と記されており、その教えを信玄も実践してのではないかと思われます。
信玄が他界する4ヵ月前に行われた三方ヶ原の戦いでも、武田軍が進軍してくることを知った家康が籠城戦の準備をしている最中に、その城の前を平然と通過し、これを好機とみた徳川軍が城から飛び出してきたところ返り討ちにして大勝利。
信玄の本来の目的は尾張の織田を潰すことではなく、なるべく無駄な争いは避けて地道に所領を固めて上洛を果たす準備を整えること。やっと、そのときが訪れ、上洛を決めた年に病気で急死しました。
天下取りの野望など抱いておらず、上洛し、朝廷から官位を授かって一国の主から国家権力の一員になる(国政や国務に関わる)ことが真の目的だったと考えられます。
そのためには無駄な血を流さずに献身的な道を進むことを選んだのでしょう。それが、生涯の合戦における「3割の引き分け」という戦歴に表れているように思います。












































-190x190.jpg)













」-190x190.jpg)
」-190x190.jpg)





























































の消滅」-190x190.jpg)





」-190x190.jpg)



















-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)








-190x190.jpg)
-190x190.jpg)




」-190x190.jpg)





-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)
















-190x190.png)
-190x190.png)


-190x190.jpg)
-190x190.jpg)









-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)


jpg-190x190.jpg)
-190x190.jpg)



-190x190.png)
-190x190.png)






-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)
」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)







-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)











-190x190.jpg)
-190x190.jpg)




-185x130.png)





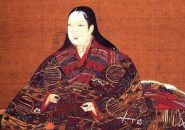

」が切腹した理由(前編)-185x130.jpg)
