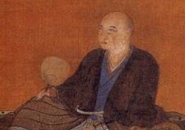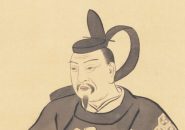名湯から秘湯まで12人の戦国武将を魅了した温泉地

現在、国内の温泉地は3038ヵ所(2016年時点)あり、利用されている源泉は18871ヵ所で、利用されていない源泉を含めると28033ヵ所あるそうです。
日本書紀(720年に完成した史料)や風土記(710年~794年にかけての記録書)に登場する古湯として、愛媛の道後温泉、兵庫の有馬温泉、和歌山の白浜温泉は日本三古湯と呼ばれています。
また、すでにエジプトでは紀元前3000〜4000年(日本は縄文時代の末期)頃に温泉が利用されており、エトルリア人は温泉施設を建設し、古代ギリシャ時代には病気や怪我の湯治として温泉が使われています。
日本では奈良時代から温泉が利用されていたわけで(利用していたかは定かでないが石器時代の遺跡からも温泉の痕跡が見つかっている)、それから何百年あとの戦国時代において温泉は湯治の定番だったわけです。
とはいえ、誰でも気軽に利用できるものではなかったようで、大名や名のある戦国武将が怪我の治癒や疲労回復のために入浴していました。そこで今回は、戦国武将ゆかりの温泉地を紹介いたします。
織田信長と岐阜・下呂温泉

画像:狩野元秀・画「織田信長」(長興寺)
羽渕家家系図(岐阜県関市の羽渕家が戦国期に記した記録)に、「天正6年(1578年)春、信長が岐阜から飛騨へ湯治に向かう道中で関(現在の関市)を通った際に当家(羽渕家)で休憩した」と記されています。
天正6年の春といえば、信長の飛騨(岐阜県北部)・美濃(岐阜県南部)の制圧が完了した頃で、連戦の疲労を癒すために飛騨国の下呂(岐阜県下呂市の下呂温泉)で湯治したそうです。
1991年に羽渕家家系図(現在は羽渕友明さんが保管)が発見されたことにより信長と下呂温泉との関わりが分かったわけですが、これまで温泉に関する信長の史料が無かったので貴重な文献ですね。
北条早雲と箱根・湯元温泉

画像:北条早雲の銅像(小田原駅)
神奈川県足柄下郡箱根町の湯元温泉は奈良時代に浄定坊という僧侶が開湯の祖と伝えられています。
北条早雲が明応2年(1493年)に足利義稙(足利将軍10代目)の勅命で伊豆(静岡県伊豆市)に攻め入る際、湯治と疲労回復のために修善寺を訪れ、伊豆を含む相模の全域を制圧し、箱根も所領の一つとなりました。
早雲は1519年に他界しましたが、菩提寺の早雲寺は箱根・湯本温泉の近辺に建てられています。早雲寺の近くにある「足払いの湯」は、早雲が足を清めたという伝説が語り継がれる温泉です。
北条氏の一族が早雲寺に参拝へ訪れた際は、治癒や疲労回復に箱根・湯本温泉を利用したと言われています。その後、豊臣秀吉が小田原城を攻める際、家臣や兵の治癒場として箱根・湯本温泉を重宝しました。
江戸時代に入って街道が整備されると、東海道に面する温泉地として旅人や商人が通うようになり、一気に知名度が上がり、箱根・湯本の名は全国に知れ渡りました。
島津義弘と宮崎・吉田温泉

画像:島津義弘の銅像(道の駅えびの)
宮崎県内で最も古い温泉である宮崎県えびの市の吉田温泉は、「鬼」の異名をもつ島津義弘ゆかりの温泉地です。
1554年に霧島山(宮崎県と鹿児島県の県境に連なる複数の火山の総称)が噴火し、昌明寺(えびの市の矢岳高原の麓の地名)に温泉が湧いたのが吉田温泉の起源。
薩摩(鹿児島西部)の領主だった義弘が日向(宮崎県)に侵攻した際、小林城の戦い(1566年)で傷を負った義弘が傷を癒すために吉田温泉で治癒したという伝説が残されています。
その数年後、日向の領主である伊東義祐と木崎原で戦い、この戦いに勝利したことで吉田温泉を含む宮崎県の全域が島津義弘の所領となりました。
木崎原の戦い(1572年)は「九州の桶狭間」と例えられるほど壮絶な戦いで、義弘は勝利したとはいえ、島津軍は8割の兵が戦死しており、相当な苦戦を強いられたことが分かりますね。
そして、天然の鹿が昌明寺の湯(現在の吉田温泉)で傷を癒しているのを見た村人が「鹿湯」と呼んでいるのを知った義弘は、その場所に大掛かりな工事を施して治癒場を造り、入浴するようになりました。
以降、1577年から増設と改築を繰り返し、家臣や兵の治癒場として利用され、治癒場を守る専用の護衛(湯守)までいたそうです。江戸時代には薩摩藩士も治癒場として利用し、西郷隆盛も吉田温泉を訪れています。












































-190x190.jpg)













」-190x190.jpg)
」-190x190.jpg)





























































の消滅」-190x190.jpg)





」-190x190.jpg)



















-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)








-190x190.jpg)
-190x190.jpg)




」-190x190.jpg)





-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)
















-190x190.png)
-190x190.png)


-190x190.jpg)
-190x190.jpg)









-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)


jpg-190x190.jpg)
-190x190.jpg)



-190x190.png)
-190x190.png)






-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)
」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)







-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)











-190x190.jpg)
-190x190.jpg)





-185x130.jpg)