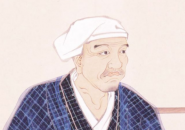命がけの墨俣一夜城

画像:墨俣一夜城の跡地に建てられた現在の墨俣城
信長の世話係から30名を束ねる足軽大将へ、のちに長浜城や姫路城の城主となり、山崎の戦いでは明智光秀を攻め、清須会議から賤ヶ岳、小牧長久手の戦い、関東・奥羽仕置を経て天下をとった秀吉。
資金も人脈もゼロの状態から天下統一を成し遂げるまで、相当な苦労があったことは言うまでもありません。いくつもの修羅場をくぐり抜け、身を粉にして信長に仕えました。
織田の家臣らの顔色も伺って気を配り、人が嫌がる仕事に率先して取り組んだ秀吉。
秀吉が30歳の頃、まだ信長が小大名で岐阜の斎藤道三を攻めているとき、信長は岐阜攻めの拠点として三角州(墨俣)に砦を築城するよう家臣らに命じます。
墨俣に砦を築いて敵の稲葉山城を監視することで、それは岐阜攻めにとって重要な過程だったのです。
しかし、いくら主君の命令とはいえ墨俣は斉藤家の領土内で、あちこち敵がいる難所。過去に佐久間信盛や柴田勝家など織田の重臣ですら築城に失敗しており、かなり難易度の高い仕事でした。
そこで白羽の矢が立ったのが秀吉。信長は、河川大工(岐阜の大工職人)と親交があった秀吉に墨俣の築城を命じ、蜂須賀正勝を大工統領とした築城が開始されます。
「危ないから別の方法を考えよう」と周囲に反対されたり、「敵の領土まで堂々と材木を運べるはずがない」とバカにされたり、それでも試行錯誤する秀吉。
そして、やっとの思いで城を完成させました。しかも驚異的なスピードで築城したことから、「まるで一晩で完成したかのようだ」と例えられ、墨俣一夜城と呼ばれていたそうです。
秀吉は、現代でも用いられる建築技法の「プレハブ式工法」で墨俣城を築城し、建築に至るまでの材木運びにもアイディアと工夫が施されていました。
まず、木曽(長野県の西)の山中で切った木材を長良川(岐阜県の中央を南下する川)の上流で加工し、加工した材木を長良川に浮かべ、水の流れを利用して長良川の下流にある墨俣まで運んだのです。
長良川の上流で伐採した材木は現地で組み立てるだけの状態に加工しておき、墨俣では流れ着いた材木を受け取って組み立てていくだけ。
これなら敵地でも短時間で築城が可能になります。とはいえ、敵兵の攻撃を受けるのは必須。稲葉山城を監視するための城なので内観は重視する必要がなく、秀吉は強度にこだわって建てたようです。
1566年に墨俣城が完成すると、その功績を認められ墨俣城の城主に任命された秀吉。翌年に信長は稲葉山城を攻め落とし、この地に岐阜城を建てました。
ここぞ!という場面を逃さなかった

画像:絵本太閤記「清須会議にて三法師を抱きかかえる秀吉」(日本城郭資料館)
一難去ってまた一難。主君がカリスマだと家臣も大忙し。信長は朝倉義景を討つべく、1570年に金ヶ崎へ進軍。しかし、後方から浅井長政が攻めてくると挟み撃ちに遭い、撤退することを決意。
その2ヶ月後、織田軍は浅井・朝倉の連合軍と姉川で戦い、秀吉は功績を残すと、1573年の「小谷城の戦い」でも功績を残し、2年後に長浜城を築城し、今浜から「長浜」へと改名しました。
秀吉が長浜と名付けるとき、信長の「長」を用いて命名したそうです。信長に気に入られようとした見え見えの行動ですが、それが秀吉の処世術であり、そういう男なんです。
その後も須磨国(兵庫県中西部)の平定や淡路国(兵庫県)統一に貢献し、着々と出世を果たす秀吉。しかし、しばらくして、秀吉の人生を大きく変える事件が起きます。
1582年、明智光秀が反乱を起こし、本能寺で信長を暗殺。このとき、秀吉は備中高松城の水攻めを終わらせ中国の毛利氏と対峙している最中でした。
すぐさま秀吉は毛利氏と和議を成立させ、2万の大軍(一説によると4万)を率いて山崎に向け進軍(中国大返し)し、明智軍を討伐。信長の仇を果たすという人生最大の名誉を秀吉は勝ち取ります。
参考記事:なぜ秀吉は天下をとれた?人生最大の分岐点となった「奇跡の26日間」に迫る
信長の死後、織田家の後継者と新たな領土の分配を決めるために開かれた清須会議では周到な根回しによって主導権を握り、賤ヶ岳や小牧長久手の戦い、毛利氏との協定や関東・奥羽仕置を経て天下人となりました。
中国大返しや山崎の戦いだけではなく、墨俣一夜城の築城や度重なる合戦の功績など、ここぞという場面でチャンスを逃さなかった秀吉。
無理難題と思うことも命を張って道を切り開き、「できっこない」と決めつけず試行錯誤しながら積極的に取り組む姿勢は現代人でも見習うこちができる要素です。
優れたコミュニケーション能力やチャンスを逃さない秀吉の決断力・行動力、無理難題を解決するための分析力や情報収集など、とるべくして天下をとった男のマネジメント能力と言えそうです。












































-190x190.jpg)













」-190x190.jpg)
」-190x190.jpg)





























































の消滅」-190x190.jpg)





」-190x190.jpg)



















-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)








-190x190.jpg)
-190x190.jpg)




」-190x190.jpg)





-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)
















-190x190.png)
-190x190.png)


-190x190.jpg)
-190x190.jpg)









-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)


jpg-190x190.jpg)
-190x190.jpg)



-190x190.png)
-190x190.png)






-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)
」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)







-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)











-190x190.jpg)
-190x190.jpg)



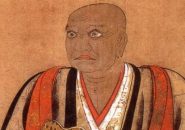


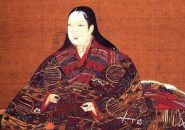


-185x130.jpg)