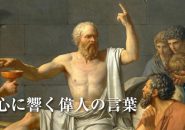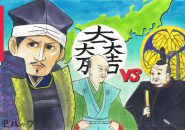酒屋を「三河屋」と呼ぶのはなぜ?

画像:三河屋酒店ミカワヤサケテン(横浜市鶴見区)
人気国民マンガ「サザエさん」に登場するサブちゃんの決め台詞といえば「こんにちわー三河屋でーす」がお馴染み。サブちゃんは酒屋の配達員で、磯野家にお酒を届けるキャラクター。
サブちゃんが言っている「三河屋」はお店の名前ではないんです。三河屋とは「酒屋」のこと。ですからサブちゃんは「こんにちわー酒屋でーす」と言っているわけなんですね。
では、なぜ酒屋のことを三河屋と呼ぶのでしょうか。
室町時代から江戸時代にかけて愛知県の南部は「三河」という地名でした。江戸に幕府を開いた徳川家康も三河地方の岡崎市出身です。
江戸の商人にも三河の出身者が多く、とくに酒を扱う商人に多かったため、「酒の商人は三河出身者が多い」ことから三河屋という呼び方になったそうですね。
ちなみにサブちゃんが働いていた酒屋の名前は「三河屋」。あえて三河屋にするなんて、ちょっとややこしい気もしますが、そこには触れないでおきましょう・・・。
ほかにも江戸には様々な地方から商人が集まっていました。三重県の商人を伊勢屋と呼び、滋賀県の商人は近江屋、新潟県の商人なら越後屋といったように出身が分かるように名乗っていたようです。
事実、三河屋も酒屋だけに限らず、たとえば豆腐屋や料理屋など三河地方の商人であれば他の商売でも三河屋という呼び名が使われていました。
「た~まや~」のライバルは「か~ぎや~」

夏の風物詩といえば花火。昔の人は花火が打ち上がるときに「た~まや~」と声を掛けましたが、これとは別に「か~ぎや~」という掛け声もありました。
江戸時代も夏になれば花火を打ち上げる風習があり、この季節が来ると2人の花火師が互いの技術を競い合うために観客を集めて花火合戦を行ったのが現在の花火大会の由来らしいです。
東京の隅田川で花火を打ち上げ、このときに上流で打ち上げていた花火師の屋号が「玉屋」、下流で花火を打ち上げた花火師の屋号が「鍵屋」でした。
江戸の観客は玉屋の打ち上げた花火を観るときには「た~まや~」と声を出し、鍵屋の花火が打ち上がれば「か~ぎや~」と声を出したわけです。
現在でも鍵屋は存在しており、創業300年を超えています。一方、玉屋は不慮の火事によって消失してしまいました。花火を見るときには思い出してみると一味違った楽しみ方ができるかもしれませんね。
蚊を殺して島流しになった人がいた

画像:PAKUTASO
光圀の話でも紹介した徳川綱吉の「生類憐みの令」ですが、生きものを殺した者は厳しい処罰を受けていました。でも、どうしてそこまで厳しいルールをつくったのでしょうか。
綱吉には後継の息子がおらず、いつになっても子を授かる気配がありませんでした。
不安になった綱吉が寺の坊さんに相談したところ、「先祖が生きものを殺していたから後継が生まれないのです。ですから、あなたは生きものを大切にしてください」とアドバイスしました。
坊さんのアドバイスに納得した綱吉は、すぐさま生類憐みの令を開始します。魚介や肉を食べてはいけないし、馬にも乗ってはいけないし、犬や猫を大切にしなければ罪人として重い罪を科せました。
ある日、一人の男が蚊を殺して逮捕されてしまいます。蚊を殺した罰として「島流しの刑」が言い渡され、その男は蚊を一匹殺しただけで見知らぬ島へ追放されてしまったのです。
ちなみに余談ですが「蚊」という文字の由来は、虫が「ぶ~ん、ぶ~ん」と音を鳴らして飛ぶことから「虫」と「文(ぶ~ん)」を組み合わせて「蚊」という字になったそうですよ。
町民の不満を爆発させた生類憐みの令は、綱吉の死後、6代目将軍になった徳川家宣が直ちに撤廃し、趣味の鷹狩りに出かけたとか。さすがに蚊を殺して島流しになるなんて・・・、今では考えられません。
さて、今回は水戸黄門と江戸時代にまつわる雑学を少し紹介しましたが、歴史って堅苦しいイメージがありますが面白いエピソードも意外と多いんですよね。歴史って、やっぱり奥が深いですね。












































-190x190.jpg)













」-190x190.jpg)
」-190x190.jpg)





























































の消滅」-190x190.jpg)





」-190x190.jpg)



















-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)








-190x190.jpg)
-190x190.jpg)




」-190x190.jpg)





-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)
















-190x190.png)
-190x190.png)


-190x190.jpg)
-190x190.jpg)









-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)


jpg-190x190.jpg)
-190x190.jpg)



-190x190.png)
-190x190.png)






-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)
」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)







-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)











-190x190.jpg)
-190x190.jpg)



-185x130.png)

-185x130.jpg)