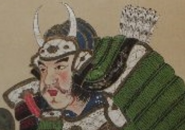戦国時代といえば「力がすべてを決める時代」と考えている方も少なくないかもしれません。実際、合戦や下克上に代表されるような「武力」を有した人間が活躍し、家名を繋げていったのは事実です。
しかし意外かもしれませんが、戦国時代にも「法律」は存在します。それを「分国法」と呼び、各国の大名が家臣や一族を統制するために制定していました。
そして現代から見ると、その内容が何とも面白いのです!
この記事では、今ではとても有り得ないような分国法の中身を見ていきながら、戦国時代の社会を考えていきます。
城内で夜に能楽を演じるのは止めてくれ!朝倉孝景条々
.jpg)
まず紹介したいのは、室町時代中期に制定されたとされる「朝倉孝景条々」という分国法です。
これは日本史の教科書に掲載されるほど、知名度および評価の高い分国法ではありますが、その一方で名前にもなっている「朝倉孝景」が生きた時代の制度と法律が噛み合っていないことから、法の制定者が誰であるのかは意見が分かれています。
この分国法で興味深い内容は、芸術についての項目でしょうか。
内容には
「夜遅くまで能楽に興じてはいけない!」
という条文が存在します。
こんなことを法律にしないといけないの?と思われるかもしれませんが、他にも芸術に関するいくつかの記載が盛り込まれており、恐らく本業そっちのけで夜遅くまで能ばかりに興じているうつけ者が少なくなかったのでしょう。
大名も大変ですね…。
落とし物は種類によって横領してよいか決める!今川仮名目録
.jpg)
次に紹介するのは、駿河の今川氏親(義元の父)が制定したとされる「今川仮名目録」です。
仮名目録は非常に完成度が高いとされ、後に執筆された分国法にもその影響が色濃くみられます。代表的なところでは、「喧嘩両成敗」の項目が武田氏によって参考にされ、後に紹介する「甲州法度ノ次第」という分国法に引用されているのです。
仮名目録で面白く、かつこの分国法が優れていた点として挙げられるのは、「落とし物」に関する項目でしょう。内容には
「流木については拾い主のものにしてよいが、漂流船については船の持ち主に返すように」
という記載が存在します。
どうしてこのような法律が必要かというと、戦国時代は「落とし物は神仏からの贈り物」と考えられており、基本的に横領が正当化されていたようなのです。したがって、大名としてはそれをどうにかして規制する必要がありました。
しかし社会の慣習として、落とし物は取得してもよいという暗黙の了解があります。そこで氏親は、「拾われると困るものだけ規制しよう」と考えたのではないでしょうか。こうすることで、慣習と上手に折り合いをつけながら新たな規制を導入したのです。
このバランス感覚が、仮名目録の優れた点と解釈されることもあります。












































-190x190.jpg)













」-190x190.jpg)
」-190x190.jpg)





























































の消滅」-190x190.jpg)





」-190x190.jpg)



















-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)








-190x190.jpg)
-190x190.jpg)




」-190x190.jpg)





-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)
















-190x190.png)
-190x190.png)


-190x190.jpg)
-190x190.jpg)









-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)


jpg-190x190.jpg)
-190x190.jpg)



-190x190.png)
-190x190.png)






-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)
」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)







-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)











-190x190.jpg)
-190x190.jpg)




」が切腹した理由(後編)-185x130.jpg)




-185x130.jpg)