お金はどこで造られていた?

現代の紙幣や硬貨は日本銀行が発行の有無を決定し、紙幣は東京都の国立印刷局で製造され、通貨は大阪府の造幣局で造られている。では、江戸時代の貨幣はどこで造られていたのだろうか。
これは、とてもわかりやすい。金貨は「金座」、銀貨は「銀座」、銅貨(銭)は「銭座」で製造され、主に全国6カ所に製造所があったとされる。
金座は現在の東京都中央区日本橋本石町にあり、ほかにも静岡県や京都、新潟県の佐渡にもあったが東京に一本化された。日本橋の本石町と言えば、現在の日本銀行の本店がある場所。
明治時代になり大阪府に造幣局が新設されると金座は役目を終え、金座の跡地には日本銀行の本店が建っている。そして、銀貨は京都と大阪、静岡や長崎で造られ、のちに東京へと銀座を移した。
もうお気づきだろうが、移転した場所が現在の東京都中央区の銀座である。ちなみに、移転する前に静岡にあった銀座の跡地は現在「両替町」という地名になっている。
銅貨は江戸時代の初期には中国から輸入していたが次第に金座や銀座で造られるようになり、もっとも多く流通することから製造数も桁違いだったとされている。
日本銀行や現在の銀座、静岡県の両替町や現在の銀行の地図記号、今でも使われている銭という呼び方や三井住友銀行のルーツなど、江戸時代から現代まで残っている足跡は多い。
歴史の足跡は意外と身近なところに隠されているのだ。












































-190x190.jpg)













」-190x190.jpg)
」-190x190.jpg)





























































の消滅」-190x190.jpg)





」-190x190.jpg)



















-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)








-190x190.jpg)
-190x190.jpg)




」-190x190.jpg)





-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)
















-190x190.png)
-190x190.png)


-190x190.jpg)
-190x190.jpg)









-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)


jpg-190x190.jpg)
-190x190.jpg)



-190x190.png)
-190x190.png)






-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)
」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)







-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)











-190x190.jpg)
-190x190.jpg)





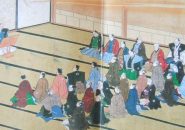
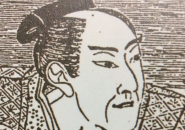


-185x130.jpg)
-185x130.jpg)


この記事へのコメントはありません。