秀吉の家臣となる
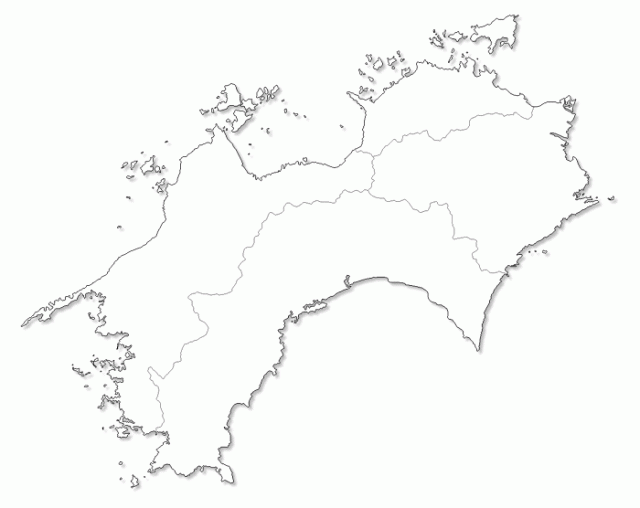
四国統一を果たした元親に不穏な知らせが届く。10万の大軍が四国を目掛けて侵攻しているというのだ。1585年6月から秀吉が開始した「四国攻め」である。
秀吉は宇喜多秀家らの軍を讃岐(香川)へ、小早川隆景、吉川元長率いる毛利軍を伊予(愛媛)へ、羽柴秀長、秀次の軍を阿波(徳島)へと同時に出陣させ、元親の支配下にある城を相次いで攻め落としていった。
元親は信頼を寄せていた家臣・谷忠澄の助言を聞き入れて、同年7月25日に降伏する。阿波、讃岐、伊予を没収され、土佐のみを残された。
京都にて秀吉に謁見し、豊臣家の家臣になることを誓った。1587年に九州攻めに従軍し、「戸次川の戦」で長男の信親を失ってしまう。1590年、小田原攻めでは水軍を率いて従軍する。
その後も2度に渡る朝鮮出兵に従軍し、1597年には土佐の治安を安定・維持させるための決まり事を記した「長宗我部元親百箇条」を書き残した。
息子へ託した遺言
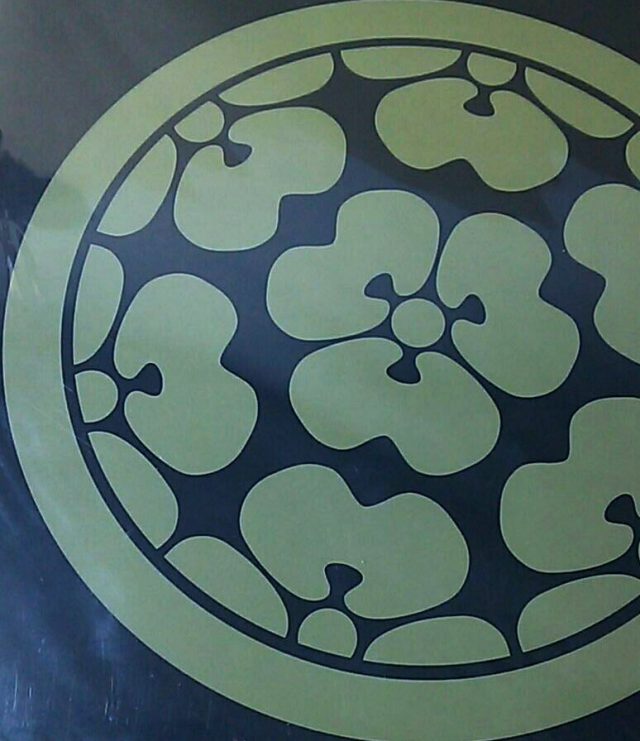
画像:長宗我部家の家紋
1598年、秀吉が死去すると、天下取りに名乗りを上げたのが徳川家康。情勢が急激に不安定となる。親は伏見屋敷に滞在し、11月26日に徳川家康の訪問を受ける。年が明けると土佐に帰国した。
1599年4月、病気療養のために京都へと向かい伏見屋敷に滞在する。23日に豊臣秀頼に謁見。しかし、病は回復せず悪化するのみで、京都や大坂から腕利きの医者が治療にあたるも、病状は悪化するばかり。
回復の見込みがないと悟った元親は、5月10日に四男の盛親(跡継ぎ)に遺言を残して5月19日、61年の生涯に幕を閉じた。
元親の死後、盛親は長宗我部氏22代当主になり、秀頼に仕える。大坂の陣では五人衆と言われ、真田信繁(幸村)らと共に奮闘するも、家康率いる徳川軍に敗北し、戦死してしまう。
元親、盛親ともに、豊臣家への忠義を尽くしたのである。以後、23代にわたり引き継がれてきた長宗我部家の歴史は、盛親の長男・盛恒(長宗我部氏23代当主)で終わった。
一芸を徹底して磨け

画像:豊臣秀吉の肖像(高台寺)
元親は猛将と恐れられたが、家臣想いの優しい武将であった。豊臣秀吉が開催したイベントに参加したとき、秀吉は元親に「饅頭」を食べさせた。しかし、元親は一口だけ食べて持ち帰ろうとした。
それを見た秀吉は、「口に合わんかったか?」と聞く。すると元親は、「殿から頂戴した縁起の良い饅頭を私一人で食べるのはもったいない。家臣にも食べさせたいので持って帰ります」と答えたそうだ。
秀吉は元親の人間性を称え、この話を残したと言われている。また、元親は勇猛果敢な戦士であるが、その源は「一芸に磨きをかけた」ことが理由と自分で述べている。
「一芸に熟達せよ。多芸を欲張るものは巧みならず」と。
槍・刀・弓・馬など武士が習得すべき技は多いが、たくさん身につけようとしても中途半端になってしまう。一つの技に秀でる者のほうが洗練されて強くなる、そう言ったのだ。
幼少の頃は色白で大人しく、内向的な性格から「姫若子」と可愛らしいニックネームをつけられ小バカにされていた元親。それが、四国統一を成し遂げる武将にまで成長した。
一芸を身につけ、その技を徹底して磨いた。継続は力なりということわざの通り、元親は死ぬまで槍の扱いを磨き、強くなるための修練に励んだ。
気配りの秀吉しかり、我慢を重ねた家康しかり、歴史に名を残す武将は努力家ということだろうか。












































-190x190.jpg)













」-190x190.jpg)
」-190x190.jpg)





























































の消滅」-190x190.jpg)





」-190x190.jpg)



















-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)








-190x190.jpg)
-190x190.jpg)




」-190x190.jpg)





-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)
















-190x190.png)
-190x190.png)


-190x190.jpg)
-190x190.jpg)









-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)


jpg-190x190.jpg)
-190x190.jpg)



-190x190.png)
-190x190.png)






-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)
」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)







-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)











-190x190.jpg)
-190x190.jpg)



-185x130.png)
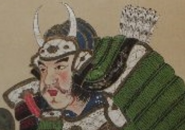








この記事へのコメントはありません。