風呂敷の語源「妙心寺」

今ではあまり見かけることが少なくなったが、昔は弁当や荷物を持ち運ぶ際に風呂敷を使っていた。昔は、お中元やお歳暮を持って行く時には風呂敷に包んで知人の家まで足を運んだものだ。
実は、この風呂敷の語源は明智光秀が関係しているという。
本能寺の変で信長を討ったあと、光秀は京都にある妙心寺(みょうしんじ)を訪ねた。妙心寺の住職に本能寺での出来事を話し、身を潜ませてほしいと頼んだが「人を殺してきた者かくまうことはできない」と断られる。
せめても情けとして、て妙心寺の住職は”お風呂”で汗と血を流すように言った。光秀が入ったとされる風呂跡が今でも妙心寺には保存されており、「明智風呂」として展示されている。
風呂といっても当時の風呂は現代で言うサウナのようなもの。蒸気で汗を流し、布で体を拭くというスタイルだった。熱々の湯を入れた釜の上に隙間のある板を敷き、その上に座って汗を流したのである。
そして、このとき、風呂の前で光秀は着ていた服や刀を包んで置いた。つまり、「風呂の前」で「布を敷いた」ことにちなんで「風呂敷」と呼ばれるようになったとか。
本能寺の変のあと、妙心寺に立ち寄った光秀の心境はどのようなものだったのか想像できない。汗や血を流しながら後悔していたのだろうか。
それとも清々しい気持ちで未来の行く末を考えていたのだろうか。いずれにしても、真実は闇の中である。
また、光秀は、本能寺の変(または山崎の戦い)で、次のような言葉を残している。
『順逆二門に無し 大道心源に徹す 五十五年の夢 覚め来れば一元に帰す』
| 正しいことと間違ったことには、一本の道しか存在しない
では、人の守るべき正しい道とは何だろうか 五十五年の間、私は夢を見ていたのかもしれない 夢から覚めた今、やっと自分を取り戻せたような気がする これまでの人生に少しの悔いも無い |
そういった意味合いが込められている。また、妙心寺には「雲龍図(うんりゅうず)」と呼ばれる天井に描かれた大きな龍も素晴らしい。これは光秀と関係ないが、ぜひ妙心寺を訪ねた際は観ておきたい。

画像:狩野探幽画「妙心寺天井の雲龍図」
江戸時代初期の絵師・狩野探幽が55歳で描いた龍だが、完成するまで8年を費やしたという。
仏教の教えでは、龍は仏を助ける存在とされており、一説によると妙心寺の雲龍図は「仏の教えを雨のように降らす」という意味が込められているそうだ。また、「水を司るとされる龍が寺院を火災から守る」とも言われている。
そして、この雲龍図は目が動く。とはいえ、絵なので実際には動いていない。「動いているように見える」のだ。さらに不思議なことに、表情が変わったように見える。
「八方睨み」と呼ばれる技法を用いて描いており、どの位置から天井を見上げても龍と目が合うようになっている。そのため、目が動いたり表情が変わって見えたりするわけだ。
妙心寺
京都府京都市右京区花園妙心寺町1(075-461-5226)
歴史上もっともミステリアスな出来事と言われる本能寺の変。
京都には、本能寺の変とつながりの深い場所がいくつかある。光秀と関係の深い「愛宕神社」と「妙心寺」。京都を訪れた際は、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。












































-190x190.jpg)













」-190x190.jpg)
」-190x190.jpg)





























































の消滅」-190x190.jpg)





」-190x190.jpg)



















-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)








-190x190.jpg)
-190x190.jpg)




」-190x190.jpg)





-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)
















-190x190.png)
-190x190.png)


-190x190.jpg)
-190x190.jpg)









-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)


jpg-190x190.jpg)
-190x190.jpg)



-190x190.png)
-190x190.png)






-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)
」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)







-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)











-190x190.jpg)
-190x190.jpg)



-185x130.jpg)



」が切腹した理由(後編)-185x130.jpg)


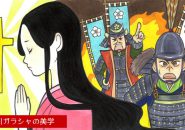


この記事へのコメントはありません。