武田四天王(武田四名臣)
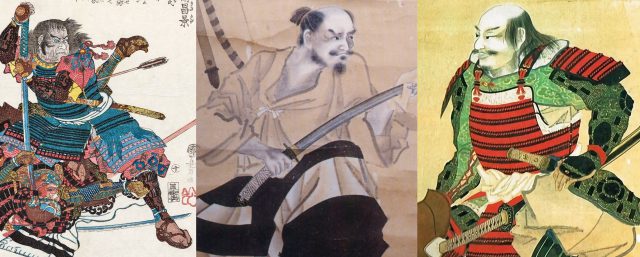
画像:左から歌川国芳・画「山県昌景」(PDJapan-oldphoto)、馬場信春、内藤昌豊(恵林寺)
山県昌景(1529年生まれ没年1575年)
昌景の兄(または甥という説もある)虎昌は武田家の重職の一人でしたが、武田信玄の長男・義信が信玄に喧嘩を売って派閥ができたときに虎昌は義信を主君に選びます。
この動きを一早く察知した昌景は信玄に「義信さんが謀反(義信事件)を起こしますよ」と事前に報告。これにより信玄は義信と虎昌を討ち、昌景は虎昌の「赤備え」を引き継ぐことになりました。
昌景の赤備えは"戦国最強の軍団"と恐れられ、武田軍の合戦において猛将ぶりを果敢に発揮しています。長篠の戦いで昌景は戦死しますが、のちに徳川四天王の井伊直政が昌景の赤備えを継承し、語り継がれることになるのです。
馬場信春(1514生まれ没年1575年)
信春は信玄の父・信虎に仕え、信玄が信虎を追放する際には信玄に加勢。つまり、父よりも息子を選んだわけです。そのため、信玄から受ける信頼は厚く、それに応えるように信春は手柄を立てていきます。
生涯で70回以上の合戦に参加し、傷を負わなかったという逸話は有名ですね。ついた異名は「不死身の鬼美濃」。また、腕っぷしの強さだけではなく知将としても信玄から頼りにされていました。
さらに、築城の技術も持ち合わせていて評価されています。長篠の戦いで窮地に陥った武田軍は、勝頼(武田家2代目)を逃がすために信春が殿を務め、迫りくる徳川軍と激突した信春は壮絶な最期で生涯に幕を閉じました。
高坂昌信(1527年生まれ没年1578年)
信玄の近習(秘書)を務めていた昌信(または春日虎綱)にとって、とくに重要な任務だったのが川中島周辺と上杉家のリサーチ。戦場でも活躍し、昌信は家臣団を率いて戦闘の最前線海津領の守将を謙信から任せられていました。
武田家記録「甲陽軍鑑」には、第4次川中島の戦いにあたり、妻女山攻撃の別働隊として昌信が戦功を挙げ、北信濃の治世にも尽力したと残されています。信玄が亡き後は勝頼を支え、ここでの役目は上杉家との和解政策。
昌信の仲介で勝頼と上杉景勝は甲越同盟を結び、外交の手腕を発揮していますね。ちなみに昌信は"逃げ弾正"と呼ばれていたそうですが、これはネガティブなニックネームではなく昌信を評価するときの誉め言葉。
昌信の退却戦は見事だったようで、合戦において最も難しいと言われているのが退く(撤退する)とき。戦術、知恵、判断能力すべてが必要になるため、合戦で頼りになる武将であったことが分かります。
内藤昌豊(1522年生まれ没年1575年)
昌豊の父・工藤虎豊は武田信虎の重臣でしたが、信虎に意見して殺されたと言われています。信玄が信虎を追放末すると昌豊は武田家に仕え、信濃平定に力を注ぎました。
昌豊の優秀さを物語る逸話として有名なのが、「信玄は昌豊に一度も感状(功績を称える書状)を贈らなかった」こと。なぜか?って、「それくらいできて当たり前」と信玄に思われるくらい優秀だったから。
ほかの家臣が感状をもらうようなことでも、昌豊にとっては"当然のこと"と評価されていたわけです。ほかの四天王に比べると目立たない存在ですが、そうした理由から表立って功績を称えていないからかもしれませんね。
戦国に名を刻む家臣団

今回は「徳川四天王」「上杉四天王」「武田四天王」を紹介しましたが、そのほかにも戦国時代の有力大名には"四天王"や"異名"がつく家臣団が記録として残されています。
たとえば、龍造寺隆信に仕えた「龍造寺四天王」や信長の天下取りを支えた「織田四天王(五大将)」、中国地方8カ国の覇者・毛利元就が従えた「毛利四天王」など、なかなか強者ぞろいですよ。
さらに、豊臣秀吉に仕えた「豊臣七将」や黒田官兵衛が率いる「黒田八虎」といった大所帯の家臣団もいますしね。
個々の武将がもつ能力がまとまり主君の戦闘能力を高めるという、武力が要だった戦国時代における大名の構図。主君にとって家臣団の能力が命綱だということがお分かりいただけると思います。
徳川四天王は、徳川家康が関ヶ原の戦いで天下を取るまで活躍した武将と言えそうです。
徳川四天王の中で酒井忠次だけは関ヶ原の戦い以前に隠居していますが、これは加齢によるもの。それ以外の3人も関ヶ原の戦い以降の活躍はそれほど知られていません。
これは徳川家康の状況によるものと考えられます。徳川家康が関ヶ原の戦いに勝つまでは、何といっても武力が重要だった。
そのため、戦うことに優秀であった4人が徳川四天王として存在した。
しかし関ヶ原の戦いで勝利し、1603年に江戸幕府を開くころには武で治めるよりも、むしろ外交で政治を進めることが多くなった。
そうなると、いわゆる武断派よりも文治派の方が徳川家康にとっては重要になった。その代表が本多正信です。
徳川家康の立場が変わることで、徳川四天王の役割の重要性も失われていった。
それが徳川四天王であったように思われます。












































-190x190.jpg)













」-190x190.jpg)
」-190x190.jpg)





























































の消滅」-190x190.jpg)





」-190x190.jpg)



















-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)








-190x190.jpg)
-190x190.jpg)




」-190x190.jpg)





-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)
















-190x190.png)
-190x190.png)


-190x190.jpg)
-190x190.jpg)









-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)


jpg-190x190.jpg)
-190x190.jpg)



-190x190.png)
-190x190.png)






-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)
」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)







-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)











-190x190.jpg)
-190x190.jpg)







-185x130.jpg)
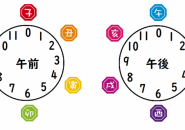
-185x130.jpg)



この記事へのコメントはありません。