その2 キリスト教の廃止

画像:踏み絵の銅板(江戸歴史資料館)
征夷大将軍になって日本を統治する立場になった家康は、「ポルトガルが世界各地を領地にするため特殊な戦術を用いて戦っている」という話を耳にします。
特殊な戦術とは、「キリスト教徒を利用した戦術」でした。世界各地にキリスト教徒を増やして、機会を見計らって戦争を起こして領地を奪うというもの。
そのことを知った家康は、一部の国を除いて貿易を禁止してキリスト教の侵入を阻止します。貿易は外国とのやり取りが主なので、貿易と同時にキリスト教が侵入するのを防ぎたかったのです。
家康が亡き後もこの制度は受け継がれ、3代目将軍の家光は徹底的にキリスト教廃止に向けて動いています。またもや、ここでも家光が”家康魂”を発揮するわけですね。
江戸時代、100人に1人がキリスト教徒だったと言われており、キリスト教の廃止は次第にエスカレートしていき社会問題となりました。
家光は1629年に「踏み絵」を導入し、キリストや聖母マリアが描かれた鉄の板を踏ませることでキリスト教徒であるか、ないかを判断。つまり、踏まなければキリスト教徒なので処罰していたわけです。
こうしてスパイを見つけるくらい徹底的にキリスト教を阻害し、日本で戦争が起きないように対策しましたが、結果的には薩摩藩や長州藩という幕府に反発する日本人によって徳川幕府は滅ぼされることになります。
敵は外部!と思っていたのに、脅威は国内にあったわけで、なんとも皮肉な話です。
その3 武家諸法度(ぶけしょはっと)で縛った
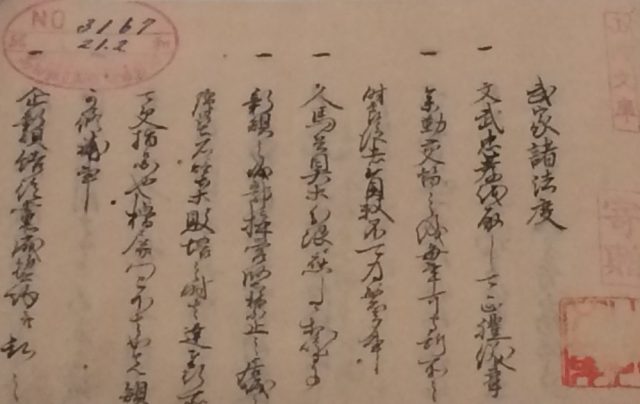
画像:№3167-武家諸法度之原本(高知城歴史博物館)
徳川幕府に歯向かわなくさせるには、強制的に重いルールを課せて縛るのも手段の一つ。そう考えた家康は、徳川家と大名たちの上下関係を明確にするために「武家諸法度」を制定。
1615年の大阪夏の陣で豊臣家を滅ぼすと、全国各地の大名を京都の伏見城に集めて13項目のルールを発表します。これがまた、なかなかタフなルールなんですよね。
1.大名は学問と武術の両方を学ぶように努力しなさい
2.大勢で酒を飲んだり遊んだりしてはダメだよ
3.犯罪者を保護したら同罪だよ(関ケ原の戦いで西軍に味方した武士とかを保護したらダメ)
4.自分の地域に犯罪者がいたら追い出しなさい
5.自分の地域に他の地域の者を住まわせてはいけませんよ
6.城を修理するときは徳川家の許可が必要で、絶対に新築はダメよ
7.隣の地域で不審な動きがあったら徳川家に通報しなさい
8.大名家の誰かが結婚するときは徳川家の許可が必要ですよ
9.地方に出張するときは決められた人数以外の部下を連れて行ってはダメですよ
10.派手な服装や身に付けるものに浪費してはダメですよ
11.大名のトップ以外が「駕籠(かご)」に乗って移動してはダメですよ
12.武士たちは節約して贅沢するのを禁止します(女遊びとか宴会を開くとか論外です)
13.大名の勤めは能力ある者を育てて質の良い政治を行うことですよ
この取り決めによって家康は、徳川家の存在が絶対的なものであることを全国に示したのです。ルールを1つでも破って逆らった場合には、家柄は消滅させられ領地も没収するなど厳しい処罰が待っていました。
実際に40人ほど大名家の者たちが処罰を受けて家柄は無くなり領地も奪われています。武家諸法度を制定した徳川家は権力を独占し、大名たちを縛り付けることに成功したわけですね。
のちに家光が、この武家諸法度のなかに参勤交代を追加し、さらに大名たちを強く縛り付けています。
大名だけではなく天皇へも「禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)」というルールを設けて対等な関係を築こうとする徳川家。
ほかにも、お寺や神社には「寺院法度(じいんはっと)」、お坊さんには「寺院諸法度(じいんしょはっと)」を定めて厳しく管理しました。
つまり、徳川家の許可なしでは勝手な行動ができないような仕組みを作ったのです。武家諸法度は徳川家の基盤となり265年にわたり引き継がれていきます。
武家諸法度の取り決めごとは最終的に21項目まで増えてしまい、大名たちにとって厳しいルールであったことは間違いなかったようです。
家康の根底にあるのは忍耐強さ?
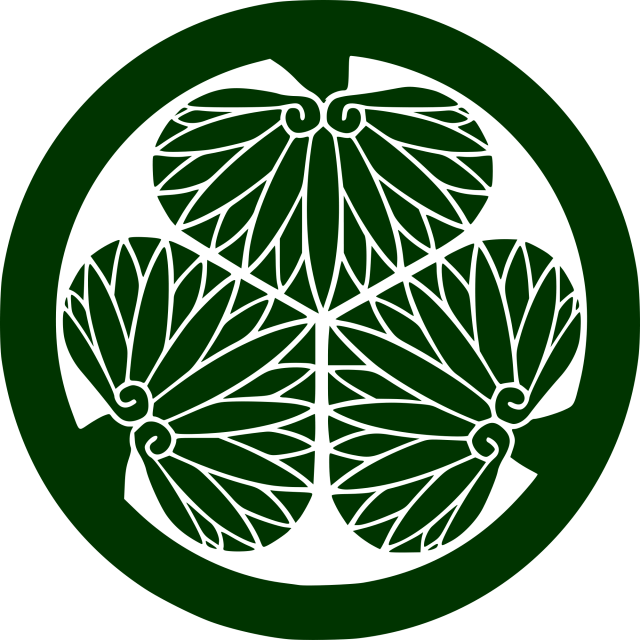
日頃から「滅びる原因は自らの中にある」と家来や自分に言い聞かせ、とにかく用心を怠らなかったそうです。それもこれも我慢が源で、気苦労の絶えない人生が家康の人格をつくったのでしょう。
まず、愛知県の岡崎市で松平家に生まれた家康は6歳のときに織田信秀(信長の父親)に捕まって織田家で人質生活を過ごします。そのあと、今川家の人質となり静岡の駿府城で生活。
桶狭間の戦いで信長が今川義元を討ち取ると人質から解放され故郷の岡崎へ帰るのですが、すでに愛知では信長が勢いを増して勢力拡大の合戦に明け暮れていた時期。
地元・岡崎への侵略を防ぐために信長と清須同盟を結び、織田家の同盟国となりました。皮肉にも、人質になっていた織田家との同盟。なんとも不思議な因果ですよね。
信長の死後、小牧・長久手で秀吉と戦いますが、秀吉から出された和解の申し出を承諾し、豊臣家のナンバー2になるわけで、ここでも天下統一を逃した家康は我慢、我慢。
秀吉の死後、関ケ原の合戦で石田三成を破ると今度は大阪夏の陣で豊臣家を滅ぼし、全国統一を成し遂げるに至りました。家康は我慢強い性格でしたが、ただ黙って耐えていたわけではありません。
人質生活では兵法や歴史書を隅々まで読み漁り、豊臣家に仕えていた頃は総勢で3000人を超える忍者を抱えて徹底的に情報を集めています。知識や知恵を学んだのはチャンスを無駄にしないための備え。
そうしたことを踏まえると、家康が定めた3つの策も納得できるような気がしますね。
用心深い性格だからこその徹底したルール

画像:徳川家康之像(駿府城)
我慢強くて慎重な性格だった家康。色々と苦労もしましたし、用心深かった家康は大名たちの資金力を減らしたりキリスト教を弾圧したり、武家諸法度など厳しいルールを定めたわけです。
その目的は、徳川将軍に逆らう要因を排除し、末永く徳川幕府を継続させるための策。思惑通りに徳川将軍は265年にわたって受け継がれ、自他共に認める絶対的な立場となりました。
15代にわたり着々と受け継がれていった徳川将軍の背景には、家康の「用心深さ」という性格がつくりだした様々な策があったことがわかります。小ネタとして、ちょっと覚えておくと面白いかもしれませんね。












































-190x190.jpg)













」-190x190.jpg)
」-190x190.jpg)





























































の消滅」-190x190.jpg)





」-190x190.jpg)



















-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)








-190x190.jpg)
-190x190.jpg)




」-190x190.jpg)





-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)
















-190x190.png)
-190x190.png)


-190x190.jpg)
-190x190.jpg)









-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)


jpg-190x190.jpg)
-190x190.jpg)



-190x190.png)
-190x190.png)






-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)
」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)







-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)











-190x190.jpg)
-190x190.jpg)









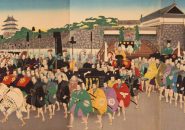

-185x130.png)

この記事へのコメントはありません。