ついに国産ワインが完成

画像:まるき葡萄酒(山梨県甲州市勝沼町)
明治10年(1877年)、土屋龍憲と高野正誠はワイン醸造法を習得するためにフランスに留学し、帰国後、宮崎光太郎を加えた3人で日本初のワイン醸造会社「大日本山梨葡萄酒会社」を設立。
これが、現在のメルシャンの発祥となった会社です。高野と土屋が醸造に注力し、宮崎は販売分野を担当。初めは順調でしたが、事業が上手くいかなくなると明治19年に「大日本山梨葡萄酒会社」は解散しました。
でも、諦めませんでした。明治24年(1891年)に土屋は山梨県にワイン醸造所「まるき葡萄酒(現在も事業を継続)」を設立し、宮崎も自宅を改良してワイン醸造所を設立します。
のちに宮崎と土屋は「甲斐産葡萄酒醸造所」を設立し、明治25年に「大黒天印甲斐葡萄酒」という本格ワインを世に送り出すことになるのです。
また、同時期(明治24年)に越後高田の川上善兵衛が岩の原葡萄園を開設し、日本の風土に適したブドウの品種改良に注力しています。川上は昭和2年にマスカット・ベーリーAの交配に成功し、国産ワインの発展に貢献した人物の一人です。
明治34年には神谷伝兵衛が茨城県の牛久でワイン醸造を開始し、2年後にフランス式の牛久シャトーを完成させています。
そして、明治37年。山梨県で小山新助が登美葡萄園でワイン醸造を開始し、やがて、この葡萄園を買収したのがサントリー(SUNTORY)の創設者である鳥井信治郎でした。
国産ワイン造りに成功したとはいえ、当時の食文化や生活スタイルには合わず、なかなか普及しなかったと言います。ワインが一般的に嗜まれるようになったのは、昭和39年(1964年)の東京オリンピックの頃からなんですよ。
細川家の"ぶどう酒"って・・・

画像:肥後熊本藩主の居城「熊本城」
さて、冒頭で紹介した「細川家が江戸時代の初期に創ったとされる"ぶどう酒"に関する書物」が発見された件ですが、細川家が自家製ぶどう酒を飲んでいたとすれば国産ワインが完成した明治25年から遡ると250年前の話。
おそらくワインではなくブドウを発酵させたものだとは思いますが、それでもブドウを原料に酒を造るという発想が日本で意識され始めたのも明治時代に入ってからですし、やはり細川家の"ぶどう酒"は貴重な史実なわけです。
豊津小笠原協会が五ケ瀬ワイナリーの協力のもと復刻させる細川家の自家製ぶどう酒、完成する日が楽しみです。
もし、ワインと同じ風味や飲み口なら、日本初の国産ワインとなり、ワインの歴史にも大きな影響を及ぼすのではないでしょうか。いずれにしても楽しみですね。
以下、西日本新聞に掲載された記事
|
熊本藩主細川家が豊前国(福岡、大分両県の一部)を治めた江戸初期、自生するブドウ科のエビヅル(通称ガラミ)でぶどう酒を造ったとする古文書が見つかり、まちおこし団体「NPO法人豊津小笠原協会」(福岡県みやこ町)が当時のぶどう酒の再興に乗り出した。宮崎県五ケ瀬町の「五ケ瀬ワイナリー」が醸造し、年内に完成予定。 400年の時を超え、細川家の「ワイン」がよみがえる。細川家は1600年代初めの約30年間、小倉藩主として豊前国を治め、現在の北九州市・小倉の礎を築いた。元首相の細川護熙氏は子孫に当たる。 ぶどう酒製造にまつわる史実は、細川家の史料を所蔵する「永青(えいせい)文庫」(東京)の古文書を調べた北九州市立自然史・歴史博物館(八幡東区)の元学芸員、永尾正剛さん(71)=福岡県行橋市=が論文「細川小倉藩の『葡萄(ぶどう)酒』製造」にまとめた。 古文書には、藩主細川忠利(1586~1641)が家臣に命じ、現在の同県みやこ町犀川大村地区に自生していたガラミでぶどう酒を造ったとする記述があったという。同じ研究をしている熊本大も、時代背景などから「薬酒」として造られたとする見解で一致している。 豊津小笠原協会は永尾さんの論文に注目し、ぶどう酒造りを模索。ガラミの栽培に乗り出し、醸造元を探した。協力を申し出た五ケ瀬ワイナリーの宮野恵支配人(62)が9月にみやこ町の自生地などを視察し、糖度と酸度を調べた結果、醸造可能と確認できた。 協会の川上義光理事長(69)が今月7日、町有志が集めた10キロのガラミを届けた。ワイナリーは地元税務署に永尾さんの文献を添え、試験醸造の届けを出して醸造に着手する。宮野支配人によると、ワインの瓶(720ミリリットル)で4~5本になりそうだという。 完成後には協会が地元でお披露目する予定。川上理事長は「細川家がみやこ町でぶどう酒を造った史実は貴重。まちおこしに生かしたい」。宮野支配人は「醸造を通じ、活動のお手伝いができればうれしい」と話している。 |
出典:2018年10月14日の西日本新聞(西日本新聞社)












































-190x190.jpg)













」-190x190.jpg)
」-190x190.jpg)





























































の消滅」-190x190.jpg)





」-190x190.jpg)



















-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)








-190x190.jpg)
-190x190.jpg)




」-190x190.jpg)





-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)
















-190x190.png)
-190x190.png)


-190x190.jpg)
-190x190.jpg)









-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
-190x190.jpg)


jpg-190x190.jpg)
-190x190.jpg)



-190x190.png)
-190x190.png)






-190x190.jpg)
-190x190.jpg)
」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)
」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)







-190x190.jpg)
-190x190.jpg)

-190x190.jpg)
-190x190.jpg)











-190x190.jpg)
-190x190.jpg)



-185x130.jpg)


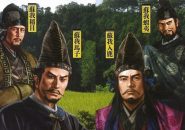






この記事へのコメントはありません。